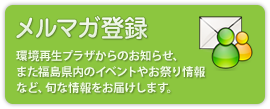ここから本文です

福島市内で2月11日、「みんなでこれからを考える『ポジティブカフェ』」が開かれました。除染や放射線影響の不安軽減に取り組む様々な方々が疑問や意見を率直に話し合い、経験を共有する目的で除染情報プラザが主催したもので、100名を超える参加がありました。
この「ポジティブカフェ」は、平成25年度から除染情報プラザで取り組んでいる活動です。今年度は、外部被ばくに関する課題と対策を考える「こども・はかる」、内部被ばくに関する課題と対策を考える「食・農」という2つのサブテーマに分かれ、これまで4回にわたりワークショップや測定などを実施してきました。その中では、顔を合わせてコミュニケーションできる場所が必要なこと、多くの情報を見聞きするより自分で体験してみることそして、多様な思いを持つ方々を尊重してつながりを持ちながら活動することの大切さが見えてきました。
こうした取組の成果を共有するために、今回のポジティブカフェでは、福島大学うつくしまふくしま未来支援センター特任研究員の開沼博さんをファシリテーターに迎え、ポジティブカフェ参加者からの活動紹介とともに、専門家も交じえたディスカッションを行いました。
「こども・はかる」のテーマでは、一般社団法人ふくしま連携復興センター事務局長の山崎庸貴さん、特定非営利活動法人ビーンズふくしまの三浦恵美里さん、福島県立福島高校スーパーサイエンス部の齊藤美緑さんから活動紹介がありました。その中では、自分で測ることの意義が共通して語られました。放射線という目に見えないものを測って、数値を見て理解することで得られる納得感など、実感のこもった発表がありました。医療法人相馬中央病院内科診療科長の越智小枝さんは、「人によって放射線に対する不安の感じ方は違う。何かを測ろうとする時、そこには目的があるため、目的に合わせて測り、その数値がどういった意味を持つのかを理解してほしい」と語りました。
「食・農」のテーマでは、山形避難者母の会代表の中村美紀さんの「福島県産の食材を避ける人が今もいる」という報告から、「風評」について話が及びました。福島大学経済経営学類教授の小山良太さんからは、「事故後、消費者に向けた農産品のPRは、『安全・安心』というスローガンばかりを伝えていることが多いため、消費者は疑念を抱き信用しない。結果をしっかりお伝えするとともに、放射線量を低下させるための対策や農家の苦労、出荷前の厳重な検査体制のことなど、ここに至るまでのプロセスも一緒に伝えることが重要だ」と指摘しました。
ディスカッションでは、ゲストレポーターを務めたタレントのなすびさんが会場を回り、放射線に関する会場からの様々な声を取り上げて、登壇者とつなげていただきました。
また、福島県立本宮高校教師・詩人の和合亮一さんが登壇し、「実は何も解決していない」現実に対する悔しさを自作の詩に託して、福島の問題を日本全体、そして世界の問題と捉えて語り続けようと呼びかけました。
除染情報プラザは、除染や放射線に関する最新の情報をお伝えするとともに、住民の皆さまとともに考えながら、皆さまの自発的な活動を後押ししていきます。

昨年8月に行われた「こども・はかる」チームのワークショップ。不安や疑問を語り合う場が必要という声も。

「言葉で伝える」ことの大切さを会場に語りかける和合さん(左)と開沼さん(右)。和合さんは自作の詩も朗読されました。

なすびさんがゲストレポーターを務め、聴講者と登壇者の意見交換も活発に行われました。
登壇者

一般社団法人ふくしま連携復興センター
事務局長 山崎庸貴氏
復興に向けた課題は複雑で、1つの組織だけでは解決できない。多様な思いを持つ多くの人と組織が連携して取り組んでいくことが大切です。

特定非営利活動法人ビーンズふくしま
三浦恵美里氏
「子どものため」など目的を明確にして、自分で放射線量を測り、数値を理解することで納得できます。福島に戻ろうか迷っている方にも、自分で調べられることを伝えたい。

福島県立福島高校スーパーサイエンス部
齊藤美緑氏
福島は線量が高いと思っている人が多いので、調べたことの伝え方にも気を配ります。来年は先輩に頼らず、一層主体的に取り組むとともに、活動を継続していきたい。

医療法人相馬中央病院
内科診療科長 越智小枝氏
都心に生まれ育ち、福島に移り住んで1年半が経ちました。いつも鳥がさえずり、水も野菜も美味しい福島は素晴らしいところ。放射線に負けず、故郷に自信を持ってほしいです。

山形避難者母の会
代表 中村美紀氏
県外避難中のお母さんに必要なのは生活に根ざした情報です。戻ろうか迷っている方には、福島に戻った方がどのように生活しているかを丁寧に伝えることを心がけています。

福島大学
経済経営学類教授 小山良太氏
事故後の情報発信が錯綜していた当時の反省を伝え、信頼を取り戻すべきです。除染や放射線について正しく伝えるには、「結果」以外にも「プロセス」を添えることが重要です。

福島県立本宮高校
教師・詩人 和合亮一氏
今も語り尽くせない悔しさや悲しみ、怒りを覚えます。でもその上で「優しさ」を携えて、そして、「情熱」を持って、福島のみなさんとともに歩んでいけたらと思います。

ゲストレポーター
タレント・俳優 なすび氏
僕にできることは、みなさんを笑顔にすること。ふるさとを応援したいという一心で、次の世代にどういうバトンを渡せるか、福島への恩返しのために本気で考え続けます。

ファシリテーター
福島大学うつくしまふくしま未来支援センター
特任研究員 開沼博氏
「福島の問題は関わりにくい」とよく聞きます。除染や放射線について、科学的な情報だけでなく、これまでの福島の歩みをもっと心に迫る言葉で伝えていきたい。