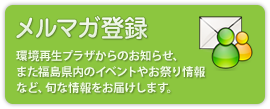ここから本文です

福島県を縦貫する阿武隈川は、県南部西郷村の源流から宮城県岩沼市と亘理町の河口まで、長さ239キロメートルを誇ります。この6月、源流域の西郷村の川谷小学校と、河口域の亘理町の荒浜小学校による交流活動が、二泊三日の日程で、西郷村で開催されました。両校は、阿武隈川の自然を考える体験学習を通じた交流を長年重ねてきました。同村での沢登りは初夏の恒例行事となっています。
今年の沢登りには、川谷小の四、五、六年生24名と、荒浜小の五年生27名が参加しました。初日、川谷小体育館で行った出会いの式では、「一本の川でつながった関係をこれからも大切にしていきましょう」と川谷小の児童があいさつ。二日目の沢登りでは、両校の児童が仲良く笑顔を見せながら、源流を歩きました。
両校教員と保護者の方々は、行事開催のための下見で施設や移動経路での放射線量の数値を確認し、今年の実施を決定しました。川谷小校舎と、荒浜小関係者が宿泊した国立那須甲子青少年自然の家は、昨年度に除染が終了した施設です。
同村には、源流域として、川や森を大切にする意識が高く、登山道や沢などの空間線量もホームページで公表してきました。村役場放射能対策課の主幹兼課長補佐の菅野一さんは、「村内には山岳会メンバーが多く、震災直後から、山に入る度にGPSによる位置情報と空間線量を計測してくれています。その情報を積極的に公表することで、不安の解消につながり、体験学習への参加者や登山者が確実に戻っています」と語りました。
きれいな阿武隈川の流れとそれを育む森を大切にしよう、という思いを両校で共有した三日間。自然の中で過ごす子どもたちの輝く眼差しが、復興へ向かう西郷村の励みとなりました。

交流活動初日、川谷小体育館で、両校児童たちの出会いの式を行った。お互いのふるさとの特長を発表後、両校で混成した沢登りの班ごとに自己紹介を行った。

昨年度の川谷小校舎の雨落ちの除染の様子。まず表層の石を除け、その下の土を除去して新しい土を入れ、洗浄した石を再び敷く作業を行った。

川谷小学校校長、菊地康則さん(左)と荒浜小学校校長、齋藤博さん。

水の冷たさに歓声を上げながら沢を渡る両校の児童たち。

沢登りの様子。両校の教員、保護者、OB、そして西郷村役場職員や支援員の皆さんが、児童の安全を守りながら沢を登った。