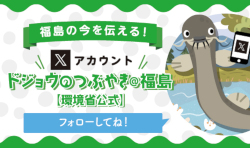- トップページ
- 除去土壌の復興再生利用について
除去土壌の復興再生利用について
▼ページ内インデックス
① 復興再生利用の目的
▼ページ内インデックス
県外最終処分に向けては、まず最終処分量を低減することが鍵となります。そのためには、中間貯蔵施設に保管される大量の除去土壌等をいかにして効率的に減容処理するか、また、その結果生じる本来貴重な資源である放射能濃度の低い土壌等を再生資材として利用可能とする技術的・制度的・社会的条件をいかに整えるかが課題となります。
2011年11月に閣議決定された基本方針において、除去土壌については、技術の進展を踏まえつつ、保管又は処分の際に可能な限り減容化を図るとともに、減容化の結果分離されたもの等、汚染の程度が低い除去土壌について、安全性を確保しつつ、再生利用等を検討する必要があると示されております。
そのため、環境省は、2016年4月に「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」を策定し、これに基づき、福島県内における除去土壌の再生利用実証事業等により安全性等に関するデータを蓄積してきました。令和7年3月に復興再生利用の基準を策定し、「復興再生利用に係るガイドライン」を公表しました。また「県外最終処分に向けたこれまでの取組の成果と2025年度以降の進め方(中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略の取りまとめ)」を公表し、今後は、これに基づき、復興再生利用の取組を推進していきます。
県外最終処分に向けたこれまでの取組の成果と2025年度以降の進め方(中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略の取りまとめ)
② 復興再生利用の流れ
▼ページ内インデックス

③ 復興再生利用に係る基準等について
▼ページ内インデックス
福島県内において再生利用の実証事業等を実施し、放射線に関する安全性の確認や具体的な管理方法の検証を行うとともに、全国民的な理解の醸成に取り組み、復興再生利用の本格化に向けた環境整備を進めています。
令和4年8月に、「中間貯蔵施設における除去土壌等の再生利用方策検討ワーキンググループ」を設置し、除去土壌の復興再生利用の基準やガイドラインの策定に向けた検討を本格化させ、令和7年3月に復興再生利用の基準として「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則」を改正するとともに、「復興再生利用に係るガイドライン」の公表を行いました。
復興再生利用の基準のポイント
- 再生資材化した除去土壌の放射性セシウム濃度
※追加被ばく線量1mSv/年を満たすように8,000Bq/kg以下を設定 - 飛散、流出の防止
- 空間線量率の測定(施工時・維持管理時)
- 生活環境の保全(騒音・振動等)
- 再生資材化した除去土壌の利用場所、利用量、放射能濃度等の記録・保存
- 事業実施者や施設管理者等との工事及び管理における役割分担等を協議
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和七年環境省令第九号)![]() (1.4MB)
(1.4MB)
関連告示![]() (595KB)
(595KB)
復興再生利用に係るガイドライン![]() (3.2MB)
(3.2MB)
復興再生利用に係るガイドライン 参考資料![]() (9.1MB)
(9.1MB)
復興再生利用に係る適切な事業実施に向けた体制整備について![]() (188KB)
(188KB)
復興再生利用について![]() (689KB)
(689KB)
④ 除去土壌の復興再生利用の流れ
▼ページ内インデックス
除去土壌を復興再生利用する際は、異物を取り除く、水分量や粒度を調整する等、除去土壌を再生資材化する作業を実施します。その後、再生資材をさらに遮へい土で覆うことで、追加被ばく線量の更なる低減を図っています。

破袋
除去土壌が入った容器を破袋し、除去土壌を取り出します。



破袋の様子
破袋後の原土
分別
除去土壌をふるいにかけ、異物(草木の根や石など)を除去します。

除去土壌をふるいに投入する様子

ふるい後の土壌

除去された異物
品質調整
復興再生利用の用途に合わせた放射能濃度で選別した土壌の水分、粒度などを改質材を使って調整します。

土壌に改質材を混ぜる様子

品質調整後の土壌
濃度確認
放射能濃度を測定し、復興再生利用の用途に合わせた放射能濃度以下の土壌であることを確認します。


放射能濃度連続分別機による濃度確認

濃度測定後の土壌

再生資材の完成

ダンプトラック荷台に積載した
土壌の濃度測定
復興再生利用
除去土壌を再生資材化する作業を終え、復興再生利用します。

飯舘村での実証事業の際の盛土造成の様子

飯舘村での盛土の様子
⑤ 実証事業・理解醸成活動
▼ページ内インデックス
1. 実証事業の実施
これまでに、南相馬市の東部仮置場(撤去済)、飯舘村長泥地区、中間貯蔵施設内の3か所において実証事業を実施し、復興再生利用の安全性に関する確認等を行ってきました。
2. 理解醸成活動の実施
これまで、除去土壌の再生利用の必要性・安全性などを伝えることを目的とした情報発信や、中間貯蔵施設・飯舘村長泥地区における再生利用実証事業の現地見学会、高校や大学等の教育機関の学生等への講義やワークショップなどを実施してきました。
今後、復興再生利用の基準の内容の発信を含め、引き続き復興再生利用の必要性・安全性等に対する全国民的な理解醸成を進めていきます。
除去土壌を用いた鉢植えの設置状況
(2025年4月時点)
- 環境省本省
大臣室、副大臣室、政務官室、中央合同庁舎5号館1階(プランター) - 関東地方環境事務所
- 東北地方環境事務所
- 環境調査研修所
- 新宿御苑
- 国立環境研究所
- 総理大臣官邸
- 復興庁
- 自民党本部
- 公明党本部
- 総務省
- 外務省
- 防衛省
- 文部科学省
- 経済産業省
- 国土交通省
- 財務省
- 法務省
- 農林水産省
- 中部地方環境事務所
- 中国四国地方環境事務所
- 近畿地方環境事務所
- 九州地方環境事務所
- 中間貯蔵事業情報センター

⑥ 参考資料・動画
▼ページ内インデックス
除去土壌の復興再生利用や放射線による健康影響について、わかりやすくお伝えする動画をご覧いただけます。
なお、本動画は、令和5年1月21日(土)新潟市にて開催した「福島、その先の環境へ。」対話フォーラムの映像を引用・加工したものです。
全編をご覧になりたい方はこちらをご覧ください。